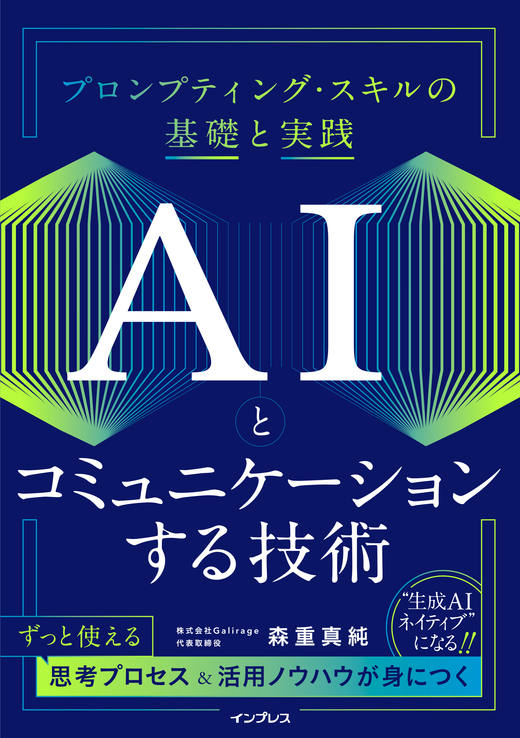
(森重真純 著:AIと共に仕事をする活用術「AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践」)
先日、ワクセル会議の記事にて次世代AI教育株式会社・東京支社長の松元春秋氏による講演を聞く機会がありました。
今回のテーマはずばりAI。
目からうろこが落ちたのは、氏の「AIは思いやりの集合体であり、自然の延長線上にある存在」とする姿勢。
AIはただの道具ではなく人の営みをつなぐものという考え方は興味深いものがありました。
そこで改めてAIについて学ぼうと読んだのが「AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践」です。
この本では、生成AI(いわゆる“生成系AI”)の仕組みや、人とAIの関係性、そしてビジネス活用におけるリスクと倫理まで幅広く学べます。
生成AIと生きる方法を学ぶ
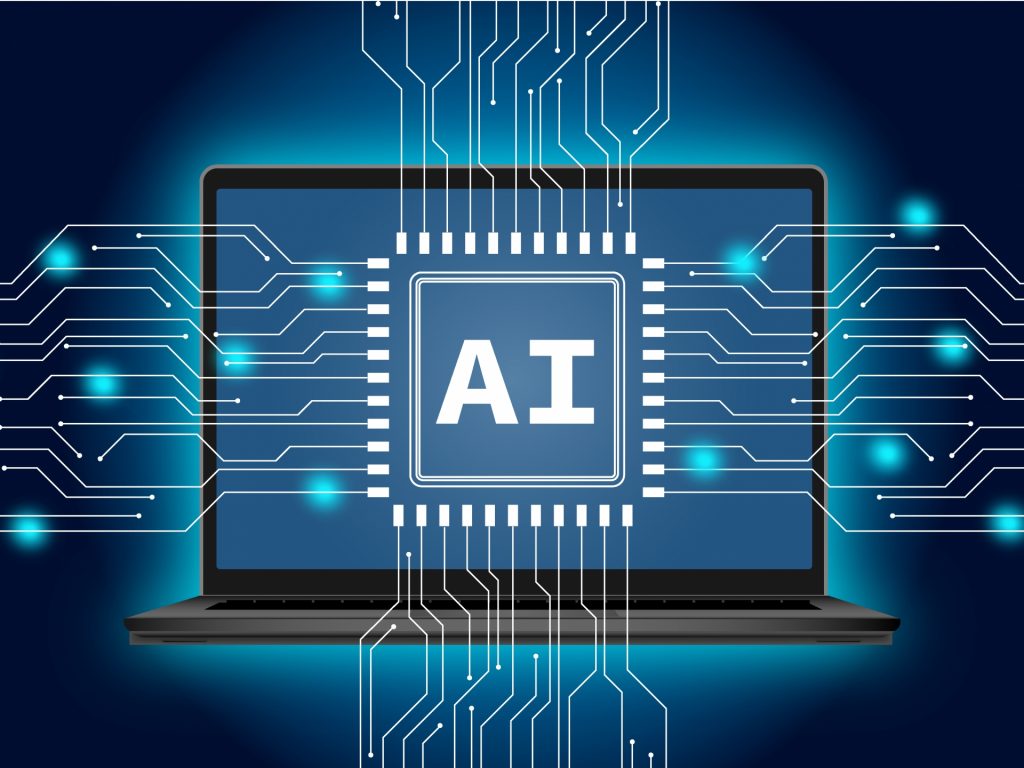
本書の著者は、慶應義塾大学大学院修士課程を修了後、日本IBMでデータサイエンティストとして活躍。
その後、生成AIに特化したコンサルティング会社・株式会社Galirageを創業し、代表取締役CEOを務めています。
「ビジネスパーソンの“時間的貧困”を解消したい」というライフビジョンのもと、AIを通じて人の思考や創造性を支援する活動を展開。
まさに“AIと共に働く未来”を体現する実践者です。
生成AIの基礎知識
ChatGPTをはじめとする生成AIを理解するには、まず“基礎の言葉”を知ることが大切です。
書籍『AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践』の第1章では、AIの全体像をつかむための40のキーワードが紹介されています。
たとえば「トランスフォーマー」はAIが文脈を理解し、自然な文章を生成するための仕組み。「トークン」は文章を分解してAIが扱える形に変える単位です。
そして「Embedding」は、言葉の意味を数値化して“似た意味”をAIが感じ取るための座標のような役割を果たします。
さらに、「RAG(検索拡張生成)」や「プロンプトインジェクション」「バイアス」など、AIを安全に、そして効果的に使うための重要な概念もわかりやすく解説。
AIをただ使うのではなく、「なぜそう動くのか」を理解することで、より深く、賢く活用できるようになる――そんな第一歩をこの本は教えてくれます。
プロンプトの書き方
AIに思い通りの答えを導いてもらうには、「正しく伝える力」が欠かせません。
書籍『AIとコミュニケーションする技術』第2章では、そのための“言葉づくり”のコツを解説しています。
生成AIは曖昧な指示には弱く、目的・条件・制約を明確に伝えるほど精度が上がります。
たとえば「ブログを書いて」ではなく、「ビジネスパーソン向けに」「落ち着いたトーンで」「400文字のコラムとして」など、誰に・どんな形で・どんな雰囲気で伝えたいのかを具体的に指示することがポイントです。
また、難しい課題ほど「ステップバイステップ・プロンプト」が効果的です。
質問を段階的に分け、AIに一歩ずつ考えさせることで、より論理的で納得感のある答えを導けます。
AIとの対話は、まさに“言葉の設計”。伝え方を磨くことで、AIはあなたの思考を正確に再現する頼もしいパートナーになります。
AIを仕事の「相棒」にするために
生成AIの真価は、“指示の工夫”によって大きく変わります。
書籍『AIとコミュニケーションする技術』第3章では、AIのポテンシャルを最大限に引き出すための実践的なテクニックが紹介されています。
まず注目したいのが「チェイン・オブ・ソート(Chain of Thought)」。これは、AIに複数の要素を順に考えさせ、深い思考を促す手法です。
単に「答えを出して」と頼むのではなく、「まず前提を整理し、次に仮説を立て、最後に結論を出す」といった段階的指示を出すことで、論理的で再現性のある出力が得られます。
さらに、AIを最新情報や社内データとつなげる「RAG(検索拡張生成)」の活用も紹介。
これにより、AIが外部データベースや社内文書を参照しながら回答できるようになります。
また、画像や音声などを扱うマルチモーダル指示も可能になり、実務の幅が一気に広がります。
AIをただのツールではなく“相棒”に変えるには、こうしたプロンプト技術を使いこなすことがカギとなるのです。
AIと「共に」仕事をするために

いかがでしたでしたでしょうか。
私自身、これまでAIはどこか無機質なツールというとらえ方をしていました。
しかし、ワクセル会議をきっけにその考えは変わり、仕事を「共に」していく「相棒」なのではないかと感じています。
現在のAIはまだまだプロンプトの組み方次第で答えが大きく変わるなど、自身の業務に活用するためには一定時用の知識と技術が必要です。
しかし、だからこそ使用者側の知見と活用術によっては、どこまでも可能性の広がるものだと思います。
AIが人の仕事を奪う、という言葉はよく聞きますが、AIと競争するのではなく「活かす」術を身に着けることがこれからの時代では不可欠ではないでしょうか。
「AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践」でAIを「相棒」として使う術を身に着けてみましょう。




